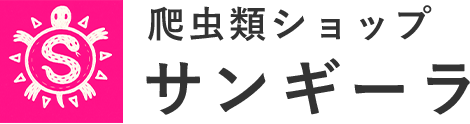乾燥対策で守る爬虫類の脱皮不全予防と早期発見ガイド
2025/11/07
爬虫類の脱皮不全が乾燥する季節に増えていませんか?乾燥が進むと、爬虫類の肌は硬くなり、うまく脱皮できず皮膚トラブルや健康リスクが高まってしまいます。乾燥対策が不十分だと、指や目、尻尾などに脱皮の殻が残り、やがて壊死や感染症へ悪化するケースも。そこで本記事では、乾燥する季節における爬虫類の脱皮不全を未然に防ぐための湿度管理や環境整備のポイント、早期発見の観察方法、万が一の際のケアに至るまで、専門的なノウハウと実践例をもとに詳しく解説します。読むことで大切なペットを脱皮不全から守り、健康で健やかな生活を長くサポートできる知識と自信が得られます。
目次
乾燥が招く爬虫類脱皮不全の原因と対策

乾燥環境が爬虫類脱皮不全を引き起こす理由
乾燥した環境は、爬虫類の脱皮不全を引き起こす主な原因のひとつです。なぜなら、脱皮の際には皮膚が適度に湿っていることで、古い皮がスムーズに剥がれやすくなるためです。反対に湿度が不足すると、皮膚が硬くなり、指や目、尻尾などに皮が残りやすくなります。
たとえば、フトアゴヒゲトカゲやヒョウモントカゲモドキなどでは、乾燥した季節になると特に脱皮不全が増加します。これは、空気中の湿度が下がることでケージ内の湿度も低下しやすく、皮膚の柔軟性が保てなくなるからです。脱皮不全を放置すると、壊死や感染症のリスクが高まるため、早めの対策が重要です。

爬虫類の脱皮不全に潜む湿度不足の危険性
湿度不足は、爬虫類の脱皮不全を悪化させる大きなリスク要因です。湿度が低い状態が続くと、皮膚の水分が失われ、古い皮が部分的に残ることで、指先や目、尾先に脱皮殻が固着しやすくなります。この状態を放置すると、血流が妨げられ壊死や二次感染を招くこともあります。
特に乾燥が進む冬や季節の変わり目は注意が必要です。実際に、レオパやカメレオンなどは湿度不足による脱皮不全が多く報告されています。湿度不足の兆候として、皮膚が白っぽくカサつく、脱皮が何日も続く、目や指先に皮が残っているなどの症状が見られます。早期発見と適切な湿度管理が、健康を守るための鍵となります。

爬虫類脱皮不全の主な原因と日常予防策
脱皮不全の主な原因には、湿度不足のほかにも、飼育環境の不適切さやストレス、栄養バランスの乱れなどが挙げられます。特に乾燥する季節は、ケージ内の湿度が下がりやすくなるため、日常的な湿度管理が不可欠です。
日常予防策としては、①定期的な霧吹きや水入れの設置、②湿度保持力の高い床材(ミズゴケやヤシガラなど)の利用、③シェルター内に湿度を保つ工夫が効果的です。さらに、脱皮前には温浴や専用スプレーで皮膚を柔らかくすることも推奨されます。脱皮不全の兆候を見逃さず、異常を感じた場合は早めに動物病院へ相談しましょう。
爬虫類の脱皮不全は湿度管理で予防できる

湿度管理が爬虫類脱皮不全予防の鍵となる理由
乾燥する季節には、爬虫類の脱皮不全が特に増加します。その主な理由は、湿度が不足することで皮膚が硬くなり、古い皮が剥がれにくくなるためです。適切な湿度管理は、脱皮不全や皮膚トラブルのリスクを低減し、健康な成長をサポートします。
実際に、ヒョウモントカゲモドキやフトアゴヒゲトカゲ、カメレオンなど多くの爬虫類種で湿度不足による脱皮不全が報告されています。特に足先や尾、目の周囲などは湿度不足の影響を受けやすく、脱皮殻が残ると壊死や感染症を引き起こすリスクも高まります。こうした事例からも、湿度管理の重要性は明らかです。
また、飼育環境の乾燥は新陳代謝の低下やストレスの要因にもなります。健康な皮膚を保ち、脱皮不全を未然に防ぐためには、日々の湿度チェックと適切な環境整備が欠かせません。

爬虫類の脱皮不全回避に適した湿度の目安
爬虫類ごとに理想的な湿度は異なりますが、脱皮不全予防にはおおむね60〜80%の湿度が推奨されます。特に乾燥する冬場やエアコン使用時は、湿度が下がりやすいため注意が必要です。
フトアゴヒゲトカゲやヒョウモントカゲモドキの場合、普段は50〜60%程度でも問題ありませんが、脱皮前後は70%前後まで湿度を上げるとスムーズな脱皮を促せます。リクガメやカメレオンなど湿度を好む種では、平常時から70%以上を保つことが重要です。
湿度が低すぎると爬虫類の皮膚が乾燥し、脱皮が途中で止まることがあります。逆に湿度が高すぎるとカビやダニの発生につながるため、種類ごとの基準を守りながら、日々の観察と調整を心がけましょう。

乾燥季の爬虫類脱皮不全対策に必須の湿度調整術
乾燥が進む季節には、湿度調整の工夫が不可欠です。代表的な方法としては、霧吹きによるケージ内の加湿、湿度保持力の高い床材(ヤシガラやミズゴケなど)の使用、水入れの設置が挙げられます。朝晩2回の霧吹きは特に効果的です。
さらに、ケージの一部に湿度の高いシェルター(ウェットシェルター)を設置すれば、爬虫類が自ら快適な場所を選ぶことができます。また、加湿器や濡れタオルをケージ周辺に置くと、全体の湿度を安定させやすくなります。
ただし、過度な加湿はカビやダニ発生の原因となるため、換気や衛生管理も同時に行いましょう。湿度調整の失敗例として、床材が常に湿っている状態は不衛生になりやすいので注意が必要です。

毎日の湿度チェックで爬虫類脱皮不全を未然に防ぐ
脱皮不全の多くは、湿度の変化に早く気付くことで未然に防ぐことができます。湿度計を使って毎日ケージ内の湿度を測定し、基準値から外れていないかを確認しましょう。特に脱皮前後は、よりこまめなチェックが必要です。
チェックの際には、ケージ内の複数箇所で湿度を測ることで、部分的な乾燥や過湿も見逃しません。朝晩やエアコン使用時など、環境が変わるタイミングでも湿度を確認し、必要に応じて加湿や換気を調整します。
実際に湿度不足に早く気付いて調整したことで、脱皮不全を防げたという飼育者の声も多く聞かれます。毎日の湿度チェックは、小さな変化を見逃さず、爬虫類の健康を守る第一歩となります。

爬虫類の脱皮不全防止へ湿度計の有効活用法
湿度計は、脱皮不全予防に欠かせないアイテムです。デジタル湿度計は数値が見やすく、複数設置することでケージ内の湿度ムラも把握できます。湿度が基準値から外れた場合は、すぐに加湿や換気を行いましょう。
湿度計の設置位置も重要です。床面、シェルター内部、ケージ中央など、複数箇所に設置することで、部分的な乾燥や過湿を早期に発見できます。また、湿度計の定期的なメンテナンスや校正も忘れずに行い、常に正確な数値を把握できるようにしましょう。
湿度計を活用した日々の管理により、脱皮不全のリスクを大幅に減らすことができます。初心者の方は、最初はこまめに数値を記録し、湿度変動の傾向を把握するのがおすすめです。
脱皮不全を防ぐ季節の環境作りのコツ

季節ごとに見直したい爬虫類脱皮環境の工夫
爬虫類の脱皮不全は、乾燥する季節に特に発生しやすくなります。季節ごとの気温や湿度の変化に合わせて、飼育環境を見直すことが重要です。とくに冬や春先は室内の湿度が下がりやすく、爬虫類の皮膚が硬くなり脱皮がうまく進まないリスクが高まります。
例えば、エアコンや暖房を使用する季節は、ケージ内の湿度が急激に低下するため、床材の見直しや水入れの設置、霧吹きの回数を増やすなどの対策が有効です。また、夏場もエアコンの冷房で乾燥する場合があるので、こまめな湿度チェックが欠かせません。脱皮不全を予防するためには、季節ごとに飼育環境の調整を定期的に実施し、爬虫類の健康を守ることが大切です。

乾燥対策が爬虫類脱皮不全予防に欠かせない理由
乾燥は爬虫類の脱皮不全の主な原因の一つです。皮膚が適度に潤っていないと、古い皮膚がスムーズに剥がれず、指や目、尻尾などに脱皮殻が残りやすくなります。特にヒョウモントカゲモドキやフトアゴヒゲトカゲなど、乾燥に弱い種は注意が必要です。
脱皮不全を放置すると、残った皮膚が血流を妨げて壊死や感染症のリスクが高まることもあります。実際、乾燥対策が不十分だった飼育者からは「指先が黒くなり始めた」「目の周りに皮膚が残ってしまった」といった声も聞かれます。こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、乾燥する季節は特に湿度管理が不可欠です。

爬虫類脱皮不全防止へケージ内の湿度コントロール術
脱皮不全を防ぐためには、ケージ内の湿度を適切にコントロールすることが必要です。湿度の目安は、種類や成長段階によりますが、おおむね50〜70%が推奨されます。湿度計を設置して、毎日のチェックを欠かさないようにしましょう。
湿度が低い場合は、朝夕2回の霧吹きや水入れの追加設置、湿度保持力の高い床材(ヤシガラ・ミズゴケなど)の導入が有効です。逆に湿度が高すぎるとカビやダニの発生リスクが増すため、ケージの換気も重要です。失敗例として、加湿しすぎてカビが発生したケースもあるため、湿度管理はバランスが肝心です。

爬虫類の隠れ家や床材が脱皮不全対策に与える影響
隠れ家(シェルター)や床材の選択は、爬虫類の脱皮不全対策に大きな影響を与えます。湿度が高めの隠れ家を用意しておくことで、脱皮前後に自ら乾燥を避ける行動をとることができます。特に湿度保持性のあるミズゴケやヤシガラなどの床材は、乾燥する季節に効果的です。
実際に、床材を乾燥しやすい新聞紙からミズゴケに変更したことで、脱皮不全が改善した例もあります。ただし、床材の湿度が高すぎると衛生面で問題が発生しやすいので、定期的な交換や清掃も忘れずに行いましょう。初心者の場合は、まず部分的に湿度の高い隠れ家を設置し、ペットが自分で環境を選べるようにするのがおすすめです。

湿度を保つための水入れ・霧吹き活用アイデア
湿度維持の基本は、水入れと霧吹きの併用です。水入れはケージ内の湿度を安定させるだけでなく、爬虫類の飲水や入浴にも役立ちます。大きめの水入れを設置し、こまめに水を交換することがポイントです。
霧吹きは朝夕2回を目安に、ケージ全体や隠れ家の周囲、床材にまんべんなく行いましょう。脱皮前は特に念入りに湿度を高めてあげると、皮膚が柔らかくなり脱皮不全の予防につながります。水入れや霧吹きを活用した湿度コントロールは、初心者から経験者まで実践しやすい方法です。失敗例としては、水入れを小さくしすぎて十分な湿度が保てなかったケースもあるため、ケージサイズや飼育種に合わせて調整しましょう。
爬虫類の乾燥対策で健康を守る方法

乾燥時期におすすめの爬虫類脱皮不全予防法
乾燥する季節は、爬虫類の脱皮不全が特に増加しやすい時期です。なぜなら、湿度が下がることで皮膚が硬化し、脱皮がスムーズに進まなくなるからです。そのため、季節ごとの湿度管理や環境整備が非常に重要となります。
代表的な予防策としては、ケージ内の湿度を常に50~70%程度に保つことが挙げられます。加湿器や霧吹きの活用、湿度保持力の高い床材(ヤシガラやミズゴケ)の使用が効果的です。また、フトアゴヒゲトカゲやヒョウモントカゲモドキなど、乾燥に弱い種は特に注意が必要です。
実際に飼育者からは、「冬場に湿度をこまめにチェックすることで、脱皮不全が激減した」といった声も多く聞かれます。特に、指や目、尻尾の先端など脱皮が残りやすい部位を重点的に観察し、異変を早期に発見することが大切です。

爬虫類の脱皮不全を防ぐ保湿テクニックの実践例
脱皮不全対策の中心となるのが、日常的な保湿テクニックです。まず、朝晩2回の霧吹きは湿度維持にとても有効です。さらに、湿度の逃げやすいケージでは、ウェットシェルター(湿った隠れ家)を設置することで、爬虫類自身が快適な湿度環境を選べます。
床材にはヤシガラやミズゴケを使い、乾燥しやすい部分には追加で水を含ませるとより効果的です。特にリクガメやカメレオンなどは、水分補給も兼ねて定期的な温浴(ぬるま湯に10分程度浸す)も推奨されます。ただし、温浴中は目を離さず、無理に皮を剥がさないことが重要です。
「脱皮不全 スプレー」など市販の保湿用品も併用すると、初心者でも簡単にケアができるというメリットがあります。これらを組み合わせて、乾燥シーズンでも脱皮不全を未然に防ぐことができます。

毎日できる爬虫類脱皮不全対策の基本ケアとは
日々のケアで最も大切なのは、観察と記録です。爬虫類の皮膚や目、指先、尻尾などを毎日チェックし、脱皮の進行や異常を早期に発見しましょう。特に、脱皮の殻が部分的に残っていないかを注意深く観察することが、早期対処に繋がります。
また、湿度計をケージ内数か所に設置し、朝晩の湿度を記録する習慣をつけると変化に気づきやすくなります。水入れの水替えや霧吹きは毎日行いましょう。床材の乾燥具合も触って確かめ、必要に応じて加湿を行うことがポイントです。
「忙しくてつい忘れてしまう」という声もありますが、日々のチェックが脱皮不全の早期発見と重症化防止に直結します。初心者でもできるシンプルなケアから始め、慣れてきたら観察記録ノートを活用するのもおすすめです。

爬虫類脱皮不全防止のための室内湿度調整ポイント
室内の湿度を適切に保つことは、脱皮不全防止の基本です。特に冬場やエアコン使用時は空気が乾燥しやすく、ケージ内湿度も下がりがちです。湿度が40%を下回ると脱皮トラブルのリスクが高まります。
加湿器の設置はもちろん、ケージ付近に濡れタオルをかけたり、水盆を増やすなどの工夫も効果的です。また、ケージの換気が悪いとカビやダニが発生しやすくなるため、湿度を保ちつつ適度な換気も忘れずに行いましょう。
「湿度が上がりすぎてしまった」という場合は、換気や除湿剤の活用でバランスを取りましょう。ヒョウモントカゲモドキやフトアゴヒゲトカゲなど、種ごとの適正湿度を把握して調整することが重要です。

乾燥シーズンの爬虫類健康チェックと環境管理
乾燥シーズンは、脱皮不全以外にもさまざまな健康リスクが高まります。爬虫類の食欲、動き、皮膚の状態、排泄物などを総合的にチェックし、異常があれば早めに対処することが大切です。
特に、脱皮不全による皮膚の変色や腫れ、壊死の兆候が見られる場合は、速やかに動物病院に相談しましょう。環境管理の基本は、温度と湿度の安定維持です。ケージ内のレイアウトや床材、シェルターの設置場所も見直し、爬虫類が自分で快適な場所を選べるように工夫しましょう。
「乾燥した日に限って元気がない」「脱皮が長引いている」といった変化にも敏感になり、必要に応じて専門家やショップに相談することで、より安全な飼育環境を維持できます。毎日の小さな気づきが、健康トラブルの未然防止に繋がります。
症状から学ぶ脱皮不全の早期発見ポイント

爬虫類脱皮不全のサインを見落とさない観察法
乾燥する季節は、爬虫類の脱皮不全が特に増加しやすいため、日々の観察が重要です。脱皮不全のサインを見逃さないためには、まず爬虫類の皮膚や体表の変化に注意を払いましょう。特に指・目・尻尾など細かい部位に古い皮膚が残っていないか、普段より色がくすんでいないか観察することが大切です。
観察のポイントとしては、毎日決まった時間にケージ内の湿度とともに、爬虫類の行動パターンや皮膚の状態をチェックする習慣をつけましょう。脱皮が近い個体には、霧吹きや湿度の高いシェルターを活用し、乾燥による脱皮不全を未然に防ぐことができます。特にフトアゴヒゲトカゲやヒョウモントカゲモドキなどは脱皮不全が起きやすいため、注意が必要です。
ユーザーの声として「毎日同じタイミングで観察することで、脱皮の兆候や異常にすぐ気付けた」という事例も多く見られます。小さな変化も記録することで、異常の早期発見につながります。

指や目に残る皮膚が爬虫類脱皮不全の兆候となる理由
爬虫類の脱皮不全では、指や目、尻尾など末端部分に古い皮膚が残りやすいのが特徴です。これは、乾燥や湿度不足、皮膚の柔軟性低下によって脱皮がスムーズに進まないため起こります。特に乾燥した季節は、自然の湿度が下がるため皮膚が硬くなり、脱皮が困難になります。
指や目に皮膚が残ると、血行障害により壊死や感染症のリスクが高まります。例えば、レオパ(ヒョウモントカゲモドキ)では指先の脱皮不全を放置すると、指が黒ずみ、最悪の場合切断に至ることもあります。目の場合、皮膚が覆ったままになると視力低下や目の炎症を招くことも。
こうしたリスクを防ぐには、湿度管理の徹底と早期発見が不可欠です。皮膚が残っているのを確認したら、無理に剥がさず動物病院や専門店に相談することが安全です。

爬虫類脱皮不全初期症状の見分け方と注意点
脱皮不全の初期症状としては、皮膚の一部が白く濁ったまま残る、脱皮後も体表がガサガサしている、動きが鈍くなるなどが挙げられます。特に乾燥した季節は、ケージ内の湿度が下がりやすいため、これらの変化が現れやすくなります。
注意点として、初期症状を見逃すと症状が進行しやすいため、日々の観察が重要です。例えば、フトアゴヒゲトカゲやカメレオンでは、脱皮不全の初期に早めに気づいて適切な湿度調整や温浴を行うことで、重症化を防ぐことができます。
また、無理に皮膚を剥がそうとすると出血や皮膚損傷の危険があるため、異常を感じた場合は専門家に相談しましょう。初心者の方は、定期的な霧吹きや湿度の高いシェルター設置など基本のケアを心がけることが大切です。

脱皮不全を疑うべき爬虫類の体表の変化例
脱皮不全を疑うべき具体的な体表の変化として、指や尻尾、目の周囲に古い皮膚が部分的に残る、皮膚がくすんで硬くなっている、脱皮後も一部が剥がれずにガサガサしているといった症状が挙げられます。特にヒョウモントカゲモドキやフトアゴヒゲトカゲでは、指先や目の脱皮不全がよく見られます。
また、脱皮後に行動が消極的になったり、食欲が低下したりする場合も注意が必要です。実際に「尻尾の先が黒ずんできた」「目の周りに白い皮膚が残った」などの相談が多く寄せられており、これらは乾燥による脱皮不全の典型的な例です。
早期発見のためには、ケージ内の湿度計チェックと合わせて、体表の変化を日々記録することが有効です。異常を感じた時は、早めに対策を講じるか専門家に相談しましょう。

爬虫類脱皮不全を早期発見する毎日のチェック法
脱皮不全を早期に発見するには、毎日決まった時間に爬虫類の体表や行動を観察する習慣が重要です。特に乾燥が強まる季節は、ケージ内の湿度管理とともに、指・目・尻尾などの末端部位に皮膚の残りがないかを重点的にチェックしましょう。
チェックリストとして、以下のポイントを毎日確認することをおすすめします。
- ケージ内の湿度が適切(50~70%程度)か確認
- 体表に古い皮膚の残りや変色がないか観察
- 指・目・尻尾の先端に異常がないかチェック
- 脱皮直後の皮膚の状態や行動の変化を記録
特に初心者の方は、湿度計や霧吹き、湿度の高いシェルターなどを活用し、日々のチェックを習慣化することが大切です。万が一異常を発見した場合は、無理に皮膚を剥がさず、速やかに動物病院や専門店へ相談しましょう。
脱皮不全時のケアや温浴実践例を解説

爬虫類脱皮不全時に役立つ温浴ケアの手順
脱皮不全の爬虫類にとって、温浴は皮膚を柔らかくし、残った脱皮殻を安全にはがすための有効なケア方法です。特に乾燥する季節は、皮膚が硬くなりやすいため、温浴によるサポートが重要になります。温浴の際は、ぬるま湯(約30度前後)を浅く張り、爬虫類の体が水没しないよう注意しながら5〜10分程度浸します。皮膚がふやけてきたら、無理に剥がさず自然にはがれるのを待つことが大切です。
温浴中は、目や指、尻尾など脱皮不全が起こりやすい部位を中心に優しく観察しましょう。脱皮殻がしつこく残る場合は、綿棒やピンセットを使う前に、必ず十分に皮膚が柔らかくなっているか確認します。温浴の頻度は、脱皮不全の進行や個体のストレス度合いを見ながら調整することがポイントです。日常的なケアとしても、乾燥しやすい季節には週1〜2回の温浴を取り入れることで、脱皮不全の予防にもつながります。

脱皮不全の爬虫類にやさしい綿棒・ピンセットの使い方
脱皮不全のケアで綿棒やピンセットを使う際は、爬虫類の皮膚を傷つけないよう細心の注意が必要です。まず、温浴や加湿で十分に皮膚を柔らかくした後、残った脱皮殻を優しく綿棒でなぞるようにして取り除きます。綿棒は水で湿らせて使うと、摩擦が減り皮膚への負担も軽減できます。ピンセットは、どうしても綿棒で取れない細かい部分にのみ使用し、力を入れすぎないようにしましょう。
特に指先や目の周り、尻尾などデリケートな部位は無理に剥がさず、皮膚が自然にはがれるのを待つ姿勢が大切です。強引に剥がすと出血や壊死、感染症のリスクが高まりますので、慎重な作業が求められます。初心者は不安な場合、動物病院や専門ショップのスタッフに相談するのも安心です。適切な道具の選び方や使い方を覚えることで、爬虫類の健康を守りながら脱皮不全ケアを行うことができます。

爬虫類脱皮不全ケアで避けたいNG行動とは
脱皮不全のケアでは、やってはいけないNG行動を知っておくことが重要です。まず、乾燥した皮膚を無理に剥がすのは絶対に避けましょう。強引な除去は皮膚を傷つけ、出血や壊死、感染症の原因となります。また、乾燥対策が不十分なままケアを続けると、再び脱皮不全を繰り返す悪循環に陥りやすくなります。
さらに、アルコールや薬品を自己判断で使うことも大きなリスクです。市販の脱皮不全用スプレーや薬品を使用する場合は、必ず使用方法や注意点を守りましょう。異常を感じたら、早めに動物病院や専門家に相談することが大切です。脱皮不全を放置してしまうと、指や目、尻尾などが壊死し、最悪の場合は切断や失明に至るケースも報告されています。正しい知識と慎重な対応が、爬虫類の健康を守る第一歩です。

温浴や加湿ケアで爬虫類脱皮不全をサポート
乾燥する季節は、ケージ内の湿度が下がりやすく、脱皮不全のリスクが高まります。そのため、温浴や加湿による環境調整が欠かせません。具体的には、朝晩の霧吹きや水入れの設置、湿度保持力の高い床材(ヤシガラやミズゴケなど)の利用が効果的です。ケージの一部に湿度が高めのシェルターを設けることで、爬虫類が自ら快適な場所を選べるようにしましょう。
温浴と並行して加湿ケアを徹底することで、皮膚が柔軟になり脱皮がスムーズに進みやすくなります。ただし、湿度が高すぎるとカビやダニの発生リスクもあるため、適度な換気や湿度計による管理が重要です。飼育環境を見直し、日々の観察を怠らないことが脱皮不全予防のカギとなります。実際に、定期的な加湿と温浴を組み合わせたことで、脱皮トラブルが減少したという飼育者の声も多く寄せられています。

爬虫類脱皮不全スプレー活用時の注意ポイント
市販の爬虫類脱皮不全スプレーは、乾燥した皮膚を柔らかくし、脱皮のサポートに役立つアイテムです。しかし、使い方を誤ると逆効果となる場合もあるため、注意が必要です。スプレーを使用する際は、必ず説明書をよく読み、用法・用量を守ることが基本です。皮膚に異常や炎症がある場合は、使用を控え、獣医師や専門家に相談しましょう。
また、スプレーの成分が目や口に入らないよう注意し、噴霧後はしっかり乾かしてからケージに戻すことが大切です。過度な使用は皮膚トラブルの原因となるため、必要な時だけ最小限にとどめましょう。脱皮不全スプレーは、日常的な乾燥対策や温浴・加湿ケアと併用することで、より高い効果が期待できます。初心者の方は、爬虫類ショップや動物病院で適切な製品や使い方についてアドバイスを受けると安心です。